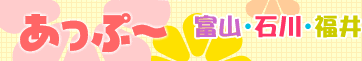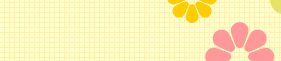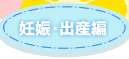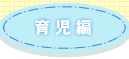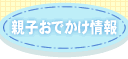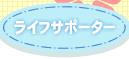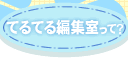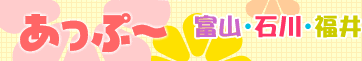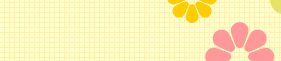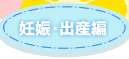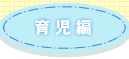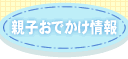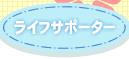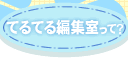|
■鼻詰まり |
| ●温かいタオルを鼻に当てて湿布する。 |
|
息が詰まらないように注意。 |
|
| ●ベビーオイルをつけた綿棒で取る。 |
入り口近くの鼻クソは綿棒でそっと取る。 |

|
なかなか鼻詰まりがとれない場合は、お医者さまに相談する。 |
|
|
|
| |
■嘔吐 |
吐き気がおさまったら、スプーン1〜2杯の湯冷ましを与えてみましょう。それで再び吐き気を誘わない様子なら30分間隔で徐々に与える量を増やしていきます。
吐物のにおいで吐き気を再度催すことがあるので、吐いたものはすぐに片付けましょう。ガーゼをぬらしてママの指に巻き、赤ちゃんの口の中を綺麗にします。余り奥まで入れると吐き気を促すので注意。
吐き気がある間は、抱いて背中をさすってあげるを楽になります。寝かせるときは、顔を横に向けて吐いても吐物が気道に入らないようにします。 |
| |
■下痢 |
下痢をするとお尻がただれやすくなります。こまめにおむつ交換をして、その都度お尻をお湯で絞ったガーゼで拭いてさっぱりさせてあげましょう。洗面器にぬるま湯を入れて、お尻を洗えばなおよいです。
お尻を乾かしてから新しいおむつを当てるのがポイント。下痢で体の水分が失われるので、普段より積極的に水分を補給しなくてはなりません。リンゴ果汁や赤ちゃん専用のイオン飲料、番茶など欲しがる飲み物を与えましょう。
母乳やミルクは、医師から特別な指示がない限り普通に与えます。食事は消化のよいものにします。食欲がないときは、無理強いはしません。 |
| |
■発熱 |
熱があると身体がほてって寝苦しいものです。布団や毛布の量を調節して、暑くないようにします。時々部屋の窓を開け新鮮な空気を入れ、気分をすっきりさせることも大切です。
冬の暖房は20度くらいでの目安で、月齢の低い赤ちゃんには、湯たんぽを寝具の足元に入れて保温します。熱の上がり際、寒そうな時は寝具を増やしたり、湯たんぽなどで暖かくしてあげます。衣類は汗の吸収のよいもので、汗をかいたらこまめに取り替えてあげましょう。
寝具同様、熱の出始めは暖かく、上がってからは暑苦しくないように調節します。着替えのとき、お湯で固く絞ったタオルで身体を拭いてあげると、さっぱりして心地よく過ごせます。
食欲があれば、母乳やミルクは欲しがるだけ与えます。離乳食は、消化のよい形に調理して食べたいだけ与え、決して無理強いはしません。水分が多くのどごしのよい食事を工夫します。
食欲がないときは、無理に食べさせる必要はありません。湯冷まし、番茶、イオン飲料やジュースなどを十分飲んでいれば心配ありません。
いつもよりこまめにあげて、家の中で静かに過ごすよう心がけることです。 |
| |
● 解熱剤は使った方がいい? ●
|
熱が高くてミルクが飲めない、眠れないというような場合には、解熱剤を使ったほうがいいですが、高熱でも比較的機嫌がよく、食事もとれ、よく眠れることが多い突発性発疹では、基本的には解熱剤を用いません。
ただ、個々の症状によってその判断は違ってきますから、使うときはかかりつけ医とよく相談することが大切です。 |
|
|
■ひきつけ |
| 重大な病気であるケースはまれで、多くは高熱が出たことによって起こる「熱性けいれん」が主。 ゆとりをもって観察しましょう。 |
| ●まず着ている服をゆるめる。 |
●呼びかけたり、揺すったりせず静かに寝かせる。 |
|
|
つばなどが出たら
ガーゼでふきとる。
静かに。
吐く場合もあるのでのどが詰まらないよう必ず、顔は横を向けておく。 |
|
| ●口の中には何もいれない。 |
|
| 舌をかむ心配はほとんどないのでスプーンやタオルなどを口にかませない。 |
|
| ●熱がないのにひきつける、くり返しひきつける、15〜20分以上けいれんが続くなどの場合は、 小児科医にみせます。 |
|
|
|
| |
■せき |
せきが止まらず辛そうなときは、赤ちゃんを立て抱きにして背中をさすってあげましょう。布団の上で、上体を起こした姿勢で背中をクッションなどに寄りかからせてあげると呼吸が楽になります。また、タンなどの分泌物の粘りが薄められて、たんが切れやすくなります。
せきが激しい時は、飲み物の刺激でさらにせきを誘うことがあります。飲んでいる時に咳き込むと、むせたり、吐いたりするので、飲み物はスプーンなどで、一口ずつ与えると安心です。
果汁などすっぱいものは避けたほうがよいでしょう。部屋の中で、湯を沸かしたり、加湿器などで、室内の湿度を高くするのも、のどに潤いを与えるのに役立ちます。特に冬場は、空気が乾燥するので気を付けて上げて下さい。 |
| |
●もっと知りたい! 薬に関するポイントアドバイス ●
|
Q.病院でもらっているけど、市販の薬は使ってはダメ?
病院で診察を受け処方された薬と市販の薬とを、同時に医師に確かめず勝手に使用するのはやめましょう。医師は、病気の症状や経過、赤ちゃんの体の大きさに応じた薬と量を処方してくれます。
市販の薬を併用してしまうと、薬のとりすぎになり、副作用を招く可能性もあるので、危険です。
Q.赤ちゃんの薬は食事の前に飲ませることが多いけど胃が荒れない?
赤ちゃんは食後に薬をあげようとしても、おなかがいっぱいになれば口をあけてくれなくなります。そのため赤ちゃんの場合、食前に投与するのがふつう。薬によっては食後の投与になる場合も。
胃に負担がかかるような薬を処方されることは赤ちゃんの場合ほとんどないので、食前投与を心配しなくても大丈夫。
Q.薬の上手な飲ませ方は?
ひとつの方法で成功しても、次はダメなこともあります。いくつかの手段を用意しましょう。
シロップ・粉薬は何かに混ぜる、スポイトや乳首を利用する、ほっぺたの内側に塗りつけるなど、薬を受け取る際に薬剤師さんに相談してみるのもよいでしょう。。 |
|
|
事故やけがの応急手当
あわてずに落ち着いて対処しましょう |
|
| |
■すり傷・切り傷 |
| ●水道水で傷口を洗う。 |
|
汚れをおとし傷を確かめる。 |
|
| ●血が出ている場合、傷口をおさえて止血する。 |
|
傷口を1〜2分しっかりおさえる。 |
|
| ●消毒し、ガーゼや包帯、バンソウコウで手当てする。 |
| 清潔なガーゼを当てて包帯やバンソウコウでとめる。 血がとまれば傷口のまわりを消毒。 |
|
|
|
| ●傷口が深い、血が止まらないなどの場合は、すぐ病院へ。 |

深い!
大きい傷!血がとまらない!! |
 |
|
|
|
|
■やけど |
| ●どんな場合も、まず水で冷やす。 |
|
水をかけ続ける。
(約15〜20分) |
| 衣服の上からやけどした場合は着せたまま水をかけ続ける。 |
|
|
| ●水をかけられない場合 |
|
水道の水をかけれない場合は水や冷たいタオルで冷やす。 |
| 浴槽やバケツに水を張り、つけて冷やすのも一案。 |
 |
|
| ●水ぶくれができた場合。 |
|
すぐに冷やしてからガーゼで手当てして病院へ。
水ぶくれをつぶさないように注意!! |
|
無理にはがすとキズが残る。
衣服に水ぶくれがくっついた場合は無理にはがさないで衣服を切る。 |
|
|
|
| |
■刺し傷 |
| ●まず刺さっているものを引き抜く。 |
|
引き抜き少し血をしぼり出す。 |
|
| ●消毒して、手当てをする。 |
|
傷口のまわりを消毒し、清潔なガーゼを当て包帯やバンソウコウでとめる。 |
|
| ●お医者さまにみせる場合。 |
|
古いクギや土の上に落ちているガラス破片などが刺さった時は破傷風の原因になることもあるので、必ずお医者さんへ! |
|
|
|
■打撲 |
| ●大声ですぐ泣いた場合 |
|
|
頭に切り傷やコブができてないか調べる。
傷の場合は手当てしコブの場合は冷たいタオルで冷やす。 |
|
| 転落したりころんだりしてすぐ泣く。 |
他に変わった様子がなければ安静にし、2〜3日観察する。 |
|
|
| ●すぐ泣かず、様子が変な場合 |
|
すぐ泣かない。
泣いた後ぐったりする。
吐く、ひきつける、発熱。
傷やはれがひどい。 |
|
赤ちゃんを動かさず
すぐ救急車を呼ぶ!
|
|
|
| |
■鼻血の止血法 |
| 細菌が繁殖しやすい夏に多い傾向。 |
| ●イスなどに座らせ、脱脂綿を鼻に詰め、小鼻を5分くらいつまみ、鼻の付け根を冷やすとほとんど止まる。 |
|
頭を後ろに
もたれさせて
座らせる。 |
|
脱脂綿を丸めて詰め、
小鼻をつまむ。
額から鼻を冷たい
タオルで冷やす。 |
|
|
|
■異物を鼻、目に入れる |
| ●鼻に入った場合 |
|
| もう一方の鼻をおさえて鼻をかむ。ピンセットなどを使って取ろうとすると、かえって奥へ入れてしまうので注意。 |
|
| ●目に入った場合。 |
|
ゴミが見えたらガーゼの先をぬらしそっととる。 |
|
| ●耳に水が入った場合。 |
|
和紙のこよりで吸い取るか、水が入った方の耳を下にして寝かせる。 |
|
| ●いずれの場合も無理に取り出そうとせずお医者さまへ。 |
|
|
|
| |
● 鼻のけが ●
|
成長する子ども時代には、思い切りぶつかって鼻がぺしゃんこになることも数回はあると覚悟してください。
幸い、たいていの場合、子どもも鼻も変形することなく元に戻ります。
鼻は、顔や頭を衝撃から守るように見事に設計されていて、鼻のおかげで、顔をぶつけても頭はけがをしないようになっているのです。
鼻がかたい面にぶつかると、薄い鼻骨が両側に押し出されて平らになります。 |
|
| |
■異物を食べる、飲む |
半数以上はたばこです。1本でこどもは致死量になると考えられています。
目配りしてください。 |
| ●牛乳、ジュースなどを200cc以上、飲ませる。 |
●吐かせてはいけない場合。 |
|
|
| のどの奥に指をつっこんで舌のつけ根を下におさえる。 |
|
|
| 異物がのどに詰まって息ができない時は背中をたたく。 |
|
|
|
|
■水に落ちる・おぼれる |
| ●意識がある場合。 |
●ぐったりしている場合はすぐ救急車を呼び、来るまで人口呼吸を。 |
泣くなど意識があるときは、水を吐かせてお医者さんへ。 |
|
| 体が冷えないよう注意する。 |
|
|
| まず、両手で下アゴを前の方へ押し出し気道を確保する。 |
|
肩の下に枕などを当てる。 |
|
| 鼻と口をお母さんの口でおおい、軽く息を吹き込む。3〜4回続けてひと休みのリズムで。 |
|
|
| ●人工呼吸でも、呼吸がもどらない場合や心臓が止まっている場合 |

| 板の上などにあお向けに寝かせ、ひとさし指と中指で押し、心臓マッサージを1秒に1回の割合で。 |
|

|
みぞおちのすぐ上あたりを
上からまっすぐ強く押す。 |
|
|
|
■動物にかまれる |
| ●すぐ、水道水で洗い流す。 |
|
| 傷口を洗い流しさらに石けんでよく洗う。 |
|
| ●消毒して、お医者さんへ。 |
|
消毒し、傷口をガーゼや包帯でとめてお医者さんへ。 |
|
| ●できれば確認を。 |
|
できれば狂犬病予防注射をしているかどうか確かめる。 |
|
|
| |
■脱水症 (日射病・熱射病・下痢・嘔吐の時) |
初期の症状 |
●唇が乾き、皮膚がカサカサ。
●尿の量や回数が減る。
●泣き声が弱々しくなり、ぐったりする。
●呼吸が苦しそうになる。 |
|
対処法 |
●風通しのよい日陰に寝かせ、衣服をゆるめて熱を逃
がす。
●水に浸したタオルで体を包む。
●嘔吐や下痢のときは、冷たすぎる水分は控え少量づ
つまめに補給。
●水やスポーツドリンクの他、電解質や糖分が適切に
配合されている「経口補水液」の摂取も最適。 |
|
|
進行した症状 |
●唇反応が鈍くなり、眠ってばかりいる。
●尿がまったく出なくなりまする。
●けいれんを起こしたり、意識がなくなり昏睡状態にな
る。 |
|
対処法 |
●一刻を争うので救急車を呼び、体内の水分を補給して
もらう。 |
|
|
| |
|